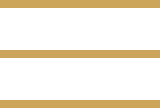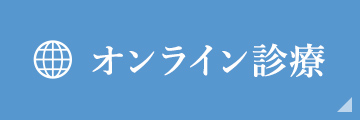なぜ難病?潰瘍性大腸炎とは

潰瘍性大腸炎は、大腸の粘膜に炎症が起こり、びらん(ただれ)や潰瘍(粘膜の深い層までえぐれた状態)ができる原因不明の慢性疾患です。厚生労働省により「指定難病」に認定されている理由は以下の通りです。
- 原因が不明:様々な要因が複雑に関与していると考えられているが、明確な原因は解明されていない
- 治療法が確立されていない:完治させる治療法はなく、症状をコントロールする対症療法が中心
- 長期の療養が必要:活動期と寛解期を繰り返し、生涯にわたる治療・管理が必要
- 患者数が一定数存在:日本では20万人以上の罹患者がいる
ただし、「難病=命を落とす病気」ではありません。適切な治療により症状をコントロールすることで、健康な人とほぼ変わらない日常生活を送ることが可能です。
潰瘍性大腸炎の症状
初期症状
- 慢性的な下痢
- 血便・粘血便(血液や粘液が混じった便)
- 下腹部の違和感・しぶり腹
進行すると現れる症状
- 腹痛
- 発熱
- 体重減少
重症化すると、1日20回以上の激しい下痢や大量の血便、高熱、脱水症状などが現れることもあります。
潰瘍性大腸炎の原因と
なりやすい人・性格
なりやすい人の特徴

- 20〜30代の若い世代(発症のピークは男性20〜24歳、女性25〜29歳。50~60代も比較的多い)
- 家族に潰瘍性大腸炎やクローン病の既往がある方
- ストレスを溜めやすい方
- 生活習慣が乱れている方
なりやすい人や性格
- ストレスを感じやすい性格
潰瘍性大腸炎とクローン病の
違い
潰瘍性大腸炎とクローン病の大きな違いは病変が生じる場所です。潰瘍性大腸炎は大腸のみに炎症が起こり、直腸から連続的に口側へ広がっていきます(ただし、例外あり)。一方、クローン病は口から肛門まですべての消化管に病変が生じる可能性があり、病変は飛び飛びに現れるのが特徴です。
また、炎症の深さにも違いがあります。潰瘍性大腸炎は粘膜の表層に炎症が限局することが多いのに対し、クローン病は腸壁の全層に炎症が及ぶため、狭窄や瘻孔(ろうこう)などの重篤な合併症を起こしやすくなります。
症状面では、潰瘍性大腸炎は血便・粘血便が特徴的ですが、クローン病では腹痛や体重減少が主症状となることが多く、肛門病変(痔ろうなど)を伴うことも少なくありません。
潰瘍性大腸炎の検査
 血液検査
血液検査- 便検査
- 大腸カメラ検査(内視鏡検査)
- 画像検査
診断基準として、持続性または反復性の粘血便・血便があり、内視鏡検査で特徴的な所見が認められ、他の疾患が除外された場合に潰瘍性大腸炎と診断されます。
内視鏡検査時に粘膜の検体を採取して病理学的検査に提出することも、診断に大きく寄与します。
潰瘍性大腸炎の治療
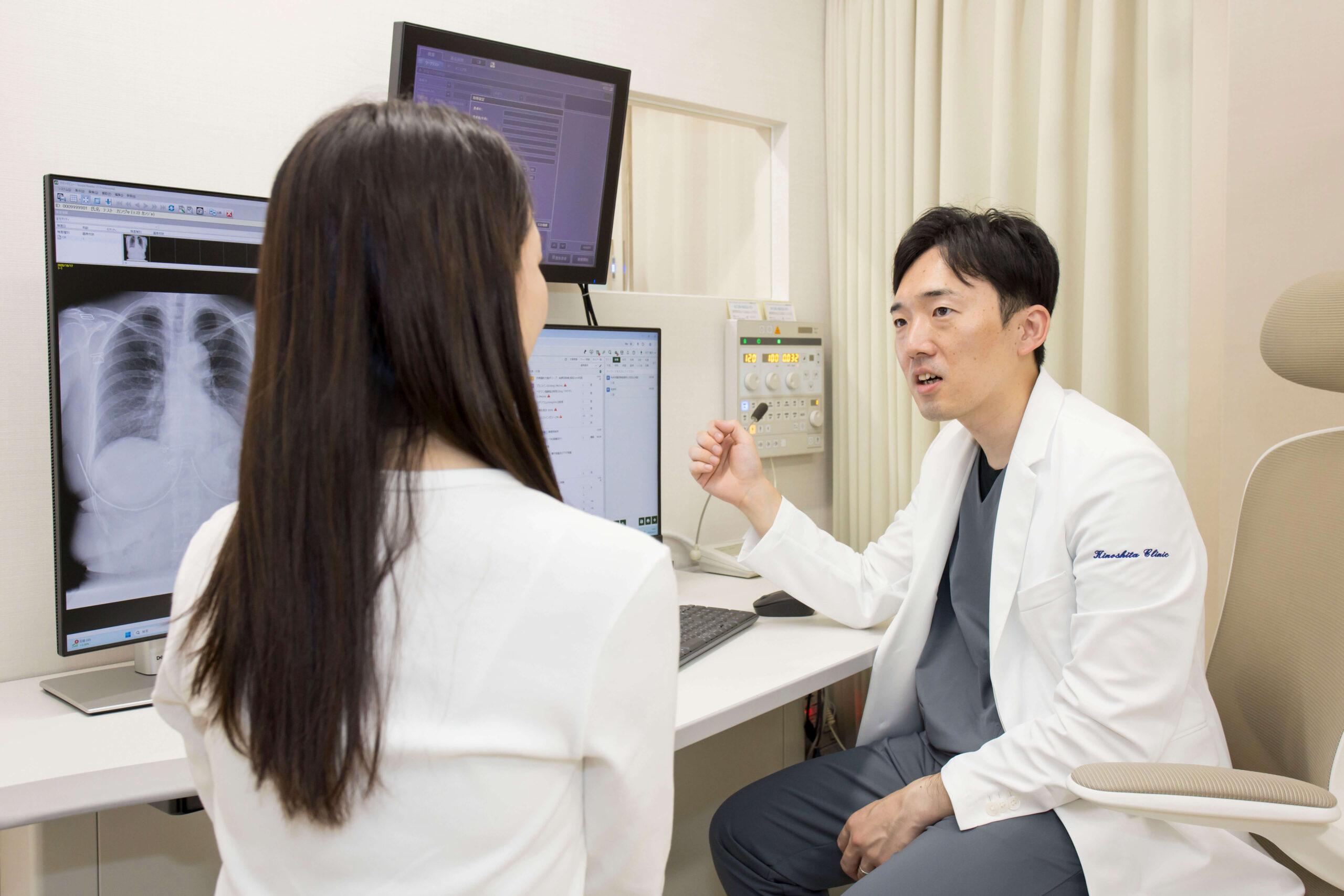 潰瘍性大腸炎の治療目標は、活動期の炎症を速やかに鎮めて寛解に導き、その状態をできるだけ長く維持することです。
潰瘍性大腸炎の治療目標は、活動期の炎症を速やかに鎮めて寛解に導き、その状態をできるだけ長く維持することです。
また近年この病気に対する治療薬の進歩は著しく、さまざまな種類の効果的な治療薬が登場しています。例えば投与経路だけでも、内服、静脈注射、皮下注射などがあります。
長年付き合っていかなければならない病気ですので、神戸三宮きのした内科 消化器内視鏡クリニックでは、患者様の病状とニーズに応じた最適な治療法を提案し、患者様と常に相談しながら治療を行うことを心がけております。また活動期かつ非常に病状が重篤な場合は、遅滞なく連携する総合病院へ紹介させて頂きます。
薬物療法
- 5-ASA製剤:炎症を抑える基本薬で、経口薬、坐剤、注腸剤があり、病変部位に応じて使い分けます。
- ステロイド:強力な抗炎症作用があるため、中等症〜重症の活動期に短期間使用します。
- 免疫調節薬:ステロイドが効かない場合や依存性がある場合に使用します。
- 生物学的製剤:TNF-α阻害薬など、難治例に使用します。最近では中等症以上の活動期にも使用します。
- JAK阻害剤:比較的新しい治療薬で、腸の炎症を抑えることで効果を発揮する飲み薬です。
- 血球成分除去療法:血液から炎症を起こす白血球の除去を行います。
外科手術
外科治療は以下のような場合に行います。
- 内科的治療で改善しない重症例
- 大量出血、穿孔、中毒性巨大結腸症などの重篤な合併症
- がん化またはその疑いがある場合
近年は肛門機能を温存する手術法も発展しており、術後のQOL(生活の質)の向上が図られています。手術が必要な場合は、提携病院をご紹介いたします。
食事療法
食事が直接的に潰瘍性大腸炎を改善させるという科学的根拠はありませんが、症状の悪化を防ぐために食事への配慮は重要です。
活動期
活動期は消化に良いものを意識した食事をおすすめしています。
- 推奨される食品:白米、うどん、食パン、卵、白身魚、鶏肉(皮なし)、豆腐
- 避けるべき食品:食物繊維の多い野菜、脂肪の多い食品、刺激物、アルコール、冷たすぎる飲食物
寛解期
厳しい食事制限は必要ありませんが、バランスの良い食事を心がけることが大切です。
- 栄養バランスを考えた食事
- 暴飲暴食を避ける
- 腸を刺激する食品は控えめに
- 個人差があるため、症状が悪化する食品は記録して把握
- ストレスにならない程度に好きな食べ物も楽しむ