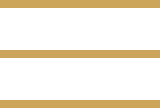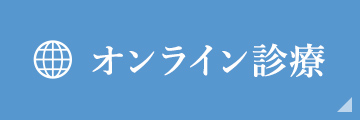- 健康診断で肝機能の異常を指摘された方へ
- 当クリニックの肝臓内科について
- このような症状は肝臓内科へご相談ください
- 肝臓の検査項目と数値の意味
- 肝臓内科で診療する疾患
- 当クリニックで対応する検査
- 当クリニックで行う治療
健康診断で肝機能の異常を
指摘された方へ
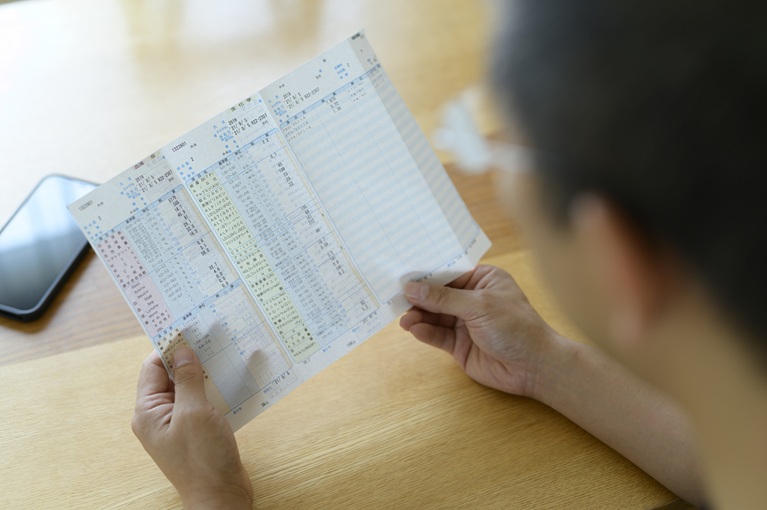 健康診断で、肝機能が異常で要精査と記載されていることはないでしょうか?
健康診断で、肝機能が異常で要精査と記載されていることはないでしょうか?
肝機能異常は、健康診断で指摘されることが比較的多い異常です。 「肝機能異常」とは、血液検査においてAST、ALT、ALP、γGTPの数値が異常な状態を指します。
原因として、B型肝炎やC型肝炎などのウイルス性肝炎、脂肪性肝疾患、自己免疫性肝炎や原発性胆汁性胆管炎などの自己免疫性肝疾患が原因となっている場合もあります。そのため、「たぶん大丈夫」と放置せずに、精密検査を受けることをおすすめします。
当クリニックの
肝臓内科について
「肝臓内科」という診療科名を見て、馴染みがないと感じられる方も多いのではないでしょうか。実は、肝臓内科は消化器内科に含まれる専門分野です。近年、専門性を重視する医療の流れから、消化器内科の中でも「胃腸」「肝臓」などの専門分野に分かれて診療を行う医療機関が増えています。
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれています。これは、肝臓の病気がある程度進行しなければ自覚症状が現れにくいためです。そのため、異常が起きても気づかないことが多く、発見された時にはすでに病気が進行しているケースも少なくありません。
消化器内科専門医・肝臓専門医である院長が行う安心の
診療
 神戸三宮きのした内科 消化器内視鏡クリニックでは、日本肝臓学会の肝臓専門医である院長が、一貫して診療を担当いたします。豊富な経験と専門知識を活かし、健康診断の異常の「その後」を丁寧にケアし、肝機能異常の原因精査・対策を迅速に行います。
神戸三宮きのした内科 消化器内視鏡クリニックでは、日本肝臓学会の肝臓専門医である院長が、一貫して診療を担当いたします。豊富な経験と専門知識を活かし、健康診断の異常の「その後」を丁寧にケアし、肝機能異常の原因精査・対策を迅速に行います。
高精度な機器を用いた肝臓の専門的な検査・診断
 高性能な超音波検査機器(ARIETTA 750 DeepInsight)による精密な評価を行い、肝硬変・脂肪肝・肝がんのリスクを早期に判別します。体に負担をかけず、肝臓の脂肪蓄積量を可視化し、わずかな異常も見逃さない検査体制を整えております。
高性能な超音波検査機器(ARIETTA 750 DeepInsight)による精密な評価を行い、肝硬変・脂肪肝・肝がんのリスクを早期に判別します。体に負担をかけず、肝臓の脂肪蓄積量を可視化し、わずかな異常も見逃さない検査体制を整えております。
各線「三宮駅」からフラワーロードをまっすぐ徒歩4分と
アクセス良好
 当クリニックはアクセス良好な場所に位置しており、定期的な検査・フォローアップが必要な患者様にも安心して通っていただけます。肝臓疾患は継続的な経過観察が重要なため、通いやすさも大切な要素と考えております。
当クリニックはアクセス良好な場所に位置しており、定期的な検査・フォローアップが必要な患者様にも安心して通っていただけます。肝臓疾患は継続的な経過観察が重要なため、通いやすさも大切な要素と考えております。
このような症状は肝臓内科へ
ご相談ください
肝臓病の初期には症状がないことが珍しくありません。早期発見、早期治療のために肝臓病のリスクがないかをチェックして、当てはまる方は受診をおすすめします。

- 疲れやすい・だるさが取れない
- 健診で肝機能の異常(AST・ALT・γ-GTP)を指摘された
- 黄疸(皮膚や白目が黄色い)
- 食欲不振
- 体重減少
- お腹の張り
- むくみが出てきた
- 皮膚がかゆい
- 尿の色が濃い
肝臓の検査項目と数値の意味
AST(GOT)・ALT(GPT)
ASTとALTは、肝臓の細胞で合成される酵素であり、アミノ酸の合成に関与しています。もし肝臓にダメージが加わり、肝細胞が損傷すると、ASTとALTが大量に血液中に放出され、血中濃度が上昇します。
ASTは血液中に放出されてから12時間前後で分解されますが、ALTの分解には50時間ほどかかることが分かっています。そのため、ALTの上昇の程度よりASTの方が高い場合は急性肝炎など肝臓の細胞に急激なダメージが生じていることが考えられます。
γ-GTP
γ-GTP(γグルタミルトランスペプチダーゼ)は、肝臓、腎臓、膵臓などの臓器に障害が生じたり、胆汁の排出路(肝内胆管、胆嚢、総胆管など)に異常があったりする場合に上昇する酵素です。特にアルコールとの関連が強いため、日常的に多くのアルコールを摂取する方はγ-GTPの値が上昇する傾向があります。
総ビリルビン
ビリルビンは、古くなった赤血球が破壊される際に生じる黄色い色素であり、肝臓で処理された後に胆汁として胆道に排出されます。肝臓の機能が低下すると、間接ビリルビンが血中に増加し、皮膚や白目が黄色く変色する黄疸という症状が現れることがあります。
肝臓内科で診療する疾患
ウイルス性肝炎
肝炎は、肝臓が炎症を起こし、発熱、黄疸、全身の倦怠感などの症状が現れる病気です。日本人の多くの肝炎はウイルス性とされてきました。A型、B型、C型、E型などのウイルスが肝炎を引き起こす原因として知られています。ウイルスの種類によって感染経路はさまざま(食べ物、血液や体液、輸血、性交渉など)です。
脂肪肝・脂肪性肝炎
脂肪肝とは、肝臓の細胞に脂肪がたくさんたまってしまった状態を指します。日本では特に男性に多く、約4割が脂肪肝にあたるとされています。
脂肪肝は肥満・糖尿病・高血圧・脂質異常症などの生活習慣病と深く関わっており、そのまま放置すると肝炎や肝硬変、さらには肝細胞がんへと進行する可能性があることが、近年の研究で明らかになってきました。実際、わが国ではウイルス性肝炎に伴う肝疾患が減少する一方で、脂肪肝に関連した肝硬変や肝がんは増加しており、大きな問題として注目されています。
特に脂肪肝の方の中でも、血液検査でALT(肝臓の炎症を示す値)が高い場合には、将来的に肝機能が悪化するリスクが高いことがわかっています。そのため、早い段階での生活習慣の見直しや適切な治療が大切です。健診等で肝機能異常(ASTまたはALTの異常)を指摘されたら、早期に医療機関を受診して下さい。
アルコール性肝障害
アルコール性肝障害は常習的に飲酒している方に発症する病気です。飲酒によりアルコール性脂肪肝になり、さらにアルコール性肝炎に進展します。治療せず放置し大量飲酒を続けると、肝炎が長く続くことによって肝硬変や肝がんに進行する場合もあります。
非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)、代謝機能不全関連脂肪性肝疾患(MAFLD)
脂肪肝の中には、アルコールの飲み過ぎが原因ではなく、生活習慣や体質が関係して起こるタイプがあります。これを「非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)」と呼びます。
NAFLDの多くは進行せず経過しますが、血液検査でALT(肝臓の炎症を示す数値)が高い場合は、将来的に肝硬変や肝がんへと進行するリスクがあることが分かっています。
さらに近年では、脂肪肝に加えて肥満・糖尿病・高血圧などの代謝異常を伴う状態を「代謝機能不全関連脂肪性肝疾患(MAFLD)」と呼ぶようになり、世界的にも注目されています。
これらの病気は、生活習慣の改善や早期の治療介入によって進行を防ぐことが可能です。ご自身の健康状態を正しく知ることが、将来の肝臓病を防ぐ第一歩になります。
「健診で脂肪肝を指摘された」「血液検査で肝機能が高いと言われた」など心当たりのある方は、ぜひ一度ご相談ください。早めのチェックと適切な対応で、肝臓を守ることができます。
自己免疫性肝炎
自己免疫性肝炎は、免疫の異常によって長期間にわたって進行する肝炎で、特に女性に多く、60歳前後の中年以降の女性に発症しやすいとされています。
薬剤性肝障害
薬剤性肝障害は、医療機関で処方された薬やドラッグストアで購入できる薬、サプリメントなどが原因となり起こる肝機能障害です。症状としては体のだるさ、食欲低下、吐き気、嘔吐、黄疸、褐色尿などを認めることがあります。患者様が健康のために購入、摂取したものが、逆に健康の害となっていることは日常の外来診療でよく経験します。そうならないためにも、肝機能異常を指摘されたら早めに肝臓専門医のいる医療機関を受診し、ご相談下さい。
肝硬変
肝硬変とは、肝臓組織が長期にわたる損傷を受けることで、肝臓が硬くなり、その機能が低下する状態です。初期の症状としては、食欲不振や疲労感などが現れ、症状が悪化すると、黄疸や腹水の蓄積、吐血、意識障害が生じる可能性があります。肝硬変に至る原因はさまざまで、これまで紹介したウイルス性、脂肪肝、アルコール性、自己免疫性肝炎などがあります。肝硬変に至ると、生命予後(寿命)が非常に悪くなりますので、肝硬変に至る前に治療介入することが重要です。
当クリニックで対応する検査
血液検査
 血液検査では、AST、ALT、γ-GTP、ALP、ビリルビンなどの値を測定し、肝臓の健康状態を確認します。数値の異常は、肝炎や脂肪肝、肝硬変などの兆候を早期にキャッチするための重要なサインとなります。
血液検査では、AST、ALT、γ-GTP、ALP、ビリルビンなどの値を測定し、肝臓の健康状態を確認します。数値の異常は、肝炎や脂肪肝、肝硬変などの兆候を早期にキャッチするための重要なサインとなります。
超音波検査(エコー検査)
 腹部超音波検査(エコー検査)は、お腹に超音波をあてて、肝臓・胆のう・すい臓・腎臓などの臓器を画像で確認する検査です。脂肪肝の有無や肝臓・膵臓の腫瘍、胆石や腎結石などを調べることができます。
腹部超音波検査(エコー検査)は、お腹に超音波をあてて、肝臓・胆のう・すい臓・腎臓などの臓器を画像で確認する検査です。脂肪肝の有無や肝臓・膵臓の腫瘍、胆石や腎結石などを調べることができます。
この検査は痛みや体への負担がなく、放射線も使用しないため、安全に受けられるのが大きな特徴です。
さらに当院では、通常のエコーに加えて「ATI(Attenuation Imaging)機能」と呼ばれる最新の測定法も導入しています。ATIでは、肝臓にどの程度脂肪がたまっているかを数値で評価することが可能です。従来は血液検査や画像所見を組み合わせて推測していた脂肪肝も、ATIにより、より客観的で正確な診断が行えるようになりました。
検査は通常のエコーと同じく短時間(10〜15分程度)で終了し、痛みもありません。安心して受けていただける検査です。
必要に応じたCT・MRI検査の実施
より詳細な診断が必要と判断された場合には、必要に応じて適切な医療機関と連携して、CTやMRIによる精密検査をご案内いたします。
当クリニックで行う治療
薬物療法
 肝臓の病気に合わせて、必要なお薬を処方します。B型肝炎やC型肝炎にはウイルスを抑える薬、肝機能を高めるためのお薬など、状態に合わせた治療が可能です。また、免疫が原因で起こる病気には免疫を調整するお薬を使うこともあります。
肝臓の病気に合わせて、必要なお薬を処方します。B型肝炎やC型肝炎にはウイルスを抑える薬、肝機能を高めるためのお薬など、状態に合わせた治療が可能です。また、免疫が原因で起こる病気には免疫を調整するお薬を使うこともあります。
生活習慣の改善
肝臓に負担をかける生活を変えることも大切です。当クリニックでは、管理栄養士による栄養指導・食事のアドバイスや飲酒量のコントロール、運動習慣の取り入れ方について具体的にご案内します。特に脂肪肝やアルコール性肝疾患の場合、生活習慣を改善するだけで症状が大きく改善することもあります。