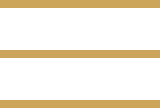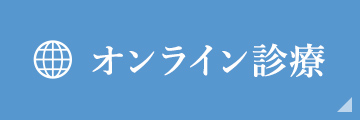機能性ディスペプシアとは
 機能性ディスペプシアとは、胃カメラ検査などで調べても胃がんや胃潰瘍・十二指腸潰瘍、慢性胃炎、逆流性食道炎などの器質的疾患が認められないにもかかわらず、慢性的な胃の不快感や痛み、胃もたれ、膨満感などの症状が続く病気です。
機能性ディスペプシアとは、胃カメラ検査などで調べても胃がんや胃潰瘍・十二指腸潰瘍、慢性胃炎、逆流性食道炎などの器質的疾患が認められないにもかかわらず、慢性的な胃の不快感や痛み、胃もたれ、膨満感などの症状が続く病気です。
日本では10人に1人が機能性ディスペプシアであると言われており、QOL(生活の質)を著しく低下させる病気として、2013年に保険診療の適応となりました。以前は「神経性胃炎」「胃下垂」「慢性胃炎」などと診断されていた症状も、現在では機能性ディスペプシアと診断されるケースが増えています。
機能性ディスペプシアの
主な症状
機能性ディスペプシアの症状は、大きく2つのタイプに分類されます。
食後愁訴症候群(PDS)
タイプ
- 食後の胃もたれ(食後膨満感)
- 早期満腹感(少し食べただけでお腹がいっぱいになる)
心窩部痛症候群(EPS)
タイプ
- みぞおちの痛み(心窩部痛)
- みぞおちの灼けるような感覚(心窩部灼熱感)
その他の症状
- 吐き気、げっぷの増加
これらの症状が6ヶ月以上前から始まり、直近3ヶ月以上続いている場合、機能性ディスペプシアと診断されます。症状は食事との関連で現れることが多く、日常生活に支障をきたすことも少なくありません。
機能性ディスペプシアになる
原因
機能性ディスペプシアの原因は完全には解明されていませんが、複数の要因が複雑に絡み合って発症すると考えられています。
胃・十二指腸の運動機能の
異常
胃は食べ物が入ると上部が拡張して貯留し(適応性弛緩)、消化後は下部が収縮して十二指腸へ送り出します(胃排出能)。この機能に障害が起こると、胃が十分に拡張せず早期満腹感が生じたり、食べ物が胃に長時間留まって胃もたれが起こります。
胃・十二指腸の知覚過敏
健康な方では問題にならない程度の胃の拡張や胃酸の刺激に対して、過敏に反応してしまう状態です。わずかな刺激で痛みや不快感を覚えやすくなり、通常の食事量でも症状が現れます。
ストレス・心理的要因
脳と腸は密接に関係しており(脳腸相関)、ストレスや過労、不安、抑うつ、過去のトラウマなどが自律神経のバランスを崩し、消化管の機能障害を引き起こします。生活上のストレスが症状を悪化させる大きな要因となっています。
生活習慣・その他の要因
- 不規則な食事習慣(早食い、暴飲暴食、夜遅い食事)
- 高脂肪食、香辛料の強い食べ物の摂取
- 喫煙、過度の飲酒
- 睡眠不足、運動不足
- ピロリ菌感染
- 感染性胃腸炎の既往
- 遺伝的要因
機能性ディスペプシアの検査
機能性ディスペプシアは、他の器質的疾患を除外することで診断される病気です。当クリニックでは以下の検査を組み合わせて、慎重に診断を行います。

- 胃カメラ検査:胃や十二指腸の粘膜に炎症、潰瘍、がんなどがないか直接観察します
- ピロリ菌検査:ピロリ菌感染の有無を確認します
- 血液検査:炎症反応、内分泌機能、全身状態を確認します
- 腹部エコー検査:肝臓、胆のう、膵臓など他の臓器の異常を確認します
- 必要に応じて腹部CT検査(近隣の医療機関と連携しています)
機能性ディスペプシアの治療
機能性ディスペプシアの治療は、薬物療法と生活習慣の改善を組み合わせて行います。患者様お一人おひとりの症状や原因に応じて、最適な治療法を選択します。
薬物療法

- 胃酸分泌抑制薬:プロトンポンプ阻害薬(PPI)、ボノプラザン(PCAB)など
- 消化管運動機能改善薬:アコチアミド、モサプリドなど
- 漢方薬:六君子湯など、症状に応じて選択
- ピロリ菌除菌薬:ピロリ菌陽性の場合
- 抗うつ薬・抗不安薬:ストレスや心理的要因が強い場合
生活習慣の改善
食事習慣の改善
- よく噛んでゆっくり食べる
- 腹八分目を心がける
- 規則正しい食事時間を守る
- 高脂肪食や刺激物を避ける
- 食後すぐに横にならない
生活習慣の改善
- 十分な睡眠時間の確保
- 適度な運動習慣
- 禁煙
- 節酒
- ストレス解消法を見つける
- 規則正しい生活リズムの確立
機能性ディスペプシアになり
食べることが怖くなった方へ
機能性ディスペプシアの症状により、食事に対する恐怖心を抱く患者様も少なくありません。しかし、絶食は避け、無理のない範囲で食事を続けることが大切です。

- まずは少量の消化の良い食事から始めましょう
- 白粥、うどん、豆腐など、胃に優しい食材を選びます
- 1回の食事量を減らし、回数を増やす少量頻回食を心がけます
- 症状が改善してきたら、徐々に通常の食事に戻していきます
症状の悪化に対する恐怖心からまったく食べられない場合は、心理的な要因も関連している可能性があります。神戸三宮きのした内科 消化器内視鏡クリニックでは、患者様の不安に寄り添いながら、必要に応じて心療内科や精神科との連携も行っています。